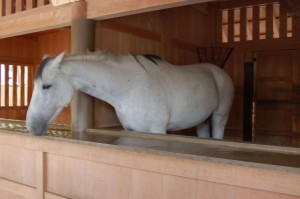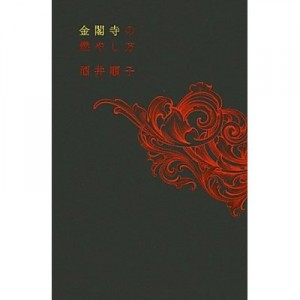ここのところ、伊達直人を名乗って、福祉施設に寄付をする人が増えてるようです。
僕も、市電で席を譲るのも気恥ずかしく思っているので、気持ちは非常にわかります。
ちなみに、年長さんの時の僕の夢は、タイガーマスクになること!だったので、タイガーマスクと聞くと、あの暗い終わりの歌の映像とイメージがぐぐっと沸き起こってきますし、続あしながおじさん(あしながじさんよりも)も好きだったので、孤児院といえばサリー(ジュディではなく)という感じ。
9年ほど前、ある友人たちと音楽イベントをやったときの収益金で、児童養護施設にプレゼントを持っていったことがあります。
クリスマスイブの野外イベントだったのですが、暖かい日で、近くに店も自販機もなかったので、途中でビールでも買ってきて売ろうかという話になりました。
イベントの主旨から、仕入れてきた値段で売ろうかと思ったのですが、ある友人が、高く売って収益でどこかに寄付でもしたほうがいいんじゃないかと言って、それもそうだということで、発泡酒の350mlを500円で売ることに。。。。
お天気のおかげもあって、結構売れたので、そこそこの収益金になりました。
それで、海の向こうに見える似島にある児童養護施設の似島学園に絵本でも買って持って行こうと言う話になりました。
一緒に行く数人で、絵本を買いに行くのも非常に面白かったです。
絵本というのは、頭というよりも、心のこやしになってるものなので、改めて手にとってみるというのも面白いし、他の人の忘れられない絵本を見るというのも面白かった。
それで絵本10冊ほどど、図書券を買って施設に持って行きました。
何か、慈善心があって訪問するというなら、気恥ずかしかったかもしれませんが、酒飲みの習性を逆手にとって稼いだお金でプレゼントするわけですから、僕たちは単にそれを運ぶだけという役割だったので、非常に気楽だったように思います。
いろいろ説明うけたり、話を聞いたりして、小さい子供とちょっと泥遊びをして帰ったのですが、非常に興味深い経験になりました。
日常的にはあまり縁がない施設なので、実情など聞けてたのが大きかったです。
両親との死別で来てる子が多いのかと思いましたが、育児放棄や家庭内の暴力など、育ての親が居ながら、育てられない事情を持ってきている子が以外とおおいということに驚きました。
そうした事情で、家庭内で大きな事件になることがここ数年増えたような気がしますが、そのとき話を聞いていたおかげで、非常にリアリティを持ってニュースに触れることができたことを記憶しています。
ささやかなプレゼントだったので、わざわざ持っていくのもご迷惑かと思ったのですが、行ってよかったと改めて思いますし、ボッタクリ価格で発泡酒を持って行ってよかったです。
伊達直人も、置いて帰るんじゃなくて、一歩足を踏み出すと、もっと何かが起こるように思います。
今、日本社会に必要なのは、物ではなく、人や社会とつながることだから。