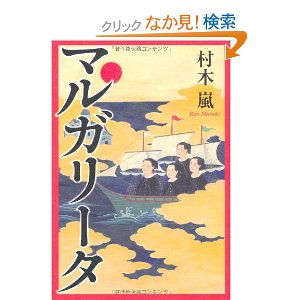僕が育った川尻町には、瀬戸鉄工という鉄工所があります。
ここの、「焼いりこ」は、カタクチイワシを高圧でプレスすると同時に加熱して煎餅状にしたものです。
愛用してる人、どこかで見かけたことある人も多いと思います。
かの白洲正子さんも、かつて愛用していたと雑誌でみかけたこともあります。
今朝の新聞に、旨み成分を入れることで、一般の塩よりも20%塩分をカットした「減塩 味ものがたり (海人の藻塩)」が紹介されていました。
塩分のとりすぎは体に負担がかかります。冷蔵庫の普及で、保存食品の塩漬けが減り、東北では心臓病が激減したという話がありましたね。
元々は普通の田舎の鉄工所のはずなんですが、、、
近くに友達が住んでいたので、建物には見覚えがあります。
社長がちょっと変わったアイデアマンなのかな?
うれしいニュースです。
川尻町とお隣りの仁方の間に、蒲刈に渡る橋がかかっています。
ここは、女猫の瀬戸と呼ばれる潮流の激しいところで、いい魚が取れるところだそうですね。
イリコといえば、小いわしを干したもの・・・というイメージですが、元々は熬海鼠。
干した海鼠のことなんですね。
日本は清からシルクや漢方薬を輸入するために、石見銀山の銀を使っていましたが、これが枯渇した後は、物々交換による貿易に切り替えようとします。
食にはうるさい清ですし、出汁を取るための乾燥物は非常に高価です。
フカヒレやツバメの巣など。
干し海鼠も非常に価値が高かったようで、川尻からも大量に出荷されたようです。
あまり知られていませんが、牡蠣の産地ではシーズンオフには中国向けの干し牡蠣をつくっているところもあるようですね。いい出汁が出るそうです。
この旨味産業を受け継いでいるのが、瀬戸内沿岸であり、この瀬戸鉄工ということかもしれないですね。
カルビーも広島発祥ですし、オタフクソースももちろん広島。
どちらも焼いた澱粉に旨味成分をからめて軽食やおやつにするというもの。
地域が伝統的に受け継いでいる文化というものは、煎じ詰めれば人の喜怒哀楽の感覚ともいえます。
この調子で、旨味産業を活性化させて、地域を豊かなものにしていって欲しいものです。