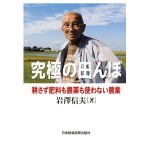僕はお米が大好きです。非常に。
お米と少しのおかずがあれば基本的には満足です。
毎日のことなので、安心できるものを食べたい。
そう思って、ここ数年、伊賀の農家から玄米で送っていただいて、コイン精米所で精米して食べています。
去年知り合った友人で、大学の隣の研究室の後輩でもあるコーセイ君が、秋田で農家の跡を継いで、不耕起栽培で米作りをしています。
その不耕起栽培をトラストの方式でやるというので、今年から一口参加させてもらうことにしました。
不耕起栽培という農法が面白そうなので、昨日2冊本を読んでみました。
岩澤信夫さんの「究極の田んぼ 」と「新しい不耕起イネつくり―土が変わる田んぼが変わる 」です。
素人なので、技術的なことはわかりませんが、、、、
戦後の高度成長の中で獲得した農業技術を否定することなく、逆に現代に必要とされる安全性や、環境に調和した技術を追求したということだと理解しました。
元々は、省力化と地力を生かすことを目的として、耕さない水田を研究していたのですが、機械で植えることや、雑草のことなどの問題を解決していくなかで、冬の間も水をはることに到達します。
不耕起水田専用の田植機も開発しました。
福岡さんも耕さない畑に、直接籾を入れた泥団子を使って稲を育てることをやっていたそうですが、インディカ米向きで、ジャポニカ米との相性はよくなかったようです。
日本には、水田による稲作の到来よりも古くから米があったとする遺物が出てきています。
おそらく、焼畑農業のような畑作による米の栽培だったのではないかと思います。
福岡さんは弥生以前の農法に近いのでしょうか。
水田による稲作は、天然の沼地で始まったようです。
雲南省あたりで里芋栽培をやってた人たちが、稲を沼の泥に植え替えて育てることから始まったとか。
畑作と違う画期的なメリットは雑草対策です。ベトナムでは、川の中に稲を植えていたので、当然水面からのぞいてるのは稲穂だけ。
船と水泳で農作業をやっていました。
岩澤さんがやってる農法は、人工的に管理されている田んぼを、一年中水を張ってる沼に変えて、微生物やイトミミズ、昆虫など生態系をつくることで、肥料や雑草、病気、冷害などに打ち勝つ強く荒々しい稲にしようということではないかと思いました。
これは、稲作や農業だけに関わる話ではなくて、建築や文化や生活、工業や社会にまで関わることが暗示されているように思います。
20世紀初頭に近代主義が生まれて、第二次大戦後に世界に広まりました。日本やドイツはその最も優秀な近代主義の生徒だったと思います。
第一次大戦以後、国家総動員体制で大戦に備えるために、日本やドイツは国を作り替えました。
戦後は、経済発展に、国家総動員体制を応用し、経済消費大国として今に至っています。
日本(や20世紀の経済消費大国)は、軌道修正を行うべき状況に至っていると誰もが思っていますが、まだ明確な方向を皆で共有出来ているとはいえません。むしろバラバラな方向を向いてる感じです。
岩澤さんの農法が面白かったのは、様々な無農薬有機栽培の人たちと違って、イデオロギーよりも先にリアリティがあるところ。
あくまで農家が生産量をあげて、経営を楽にするために、自然農法を選択しようと言うところです。
戦後65年の間、多くのものを捨てて、多くのものを獲得しました。
20年前に非効率的であるから捨てられた物は、現代では効率的であるかもしれない。
岩澤さんが苦心して開発した不耕起栽培の田んぼが、戦後に近代化された田んぼよりも優れていて、それが4400年前の天然の沼のようなものであるなら、テクノロジーがぐるっと一周りした感じで、非常に面白いと思うのです。