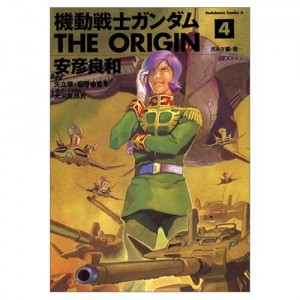以前バルセロナに行ったとき、バルセロナ第二のサッカークラブであるエスパニョールってどうなの?と地元の人に聞いたら、あそこのサポーター連中は、マドリッドの御用聞きばっかりの金持ち連中ばかりだ。と言われました。
ということは、FCバルサのサポーターは、マドリッド嫌いの庶民が多いのかという感じで話は終わりました。
その後、モンジュイックの丘に行き、ミースのバルセロナパビリオンや、磯崎新の体育館を見て、ミロ美術館に行く途中、巨大なスタジアムがあった。
そこが、今回建設された新スタジアムに移転する前の、エスパニョールのスタジアムでした。
バルセロナオリンピックのメインスタジアムをそのまま使ってたようです。
広島のビッグアーチのようなもんですね。
スタジアムの前に小さなコンテナハウスがあって覗いてみると、エスパニョールのオフィシャルショップでした。
バルセロナの至ところにあるFCバルサのオフィシャルショップに比べると、閑散としたそのショップに、そのクラブのバルセロナでの微妙な位置関係が垣間見えたのでした。
日本に帰ってきて、スペインで感じた暗い影の部分が気になったので、スペイン内戦のことを調べてみました。
第二次大戦の前哨戦としておこったスペイン内戦は、ピカソの「ゲルニカ」や、キャパの「崩れ落ちる兵士」、ヘミングウェイの「誰がために鐘は鳴る」など、当時の欧州のクリエイター達が様々な形でその内容を表現しています。
選挙で多数派となった、スペインの社会主義、無政府主義、共産主義等の人民戦線政府が成立し、反対派だった王党派やカソリック、全体主義者などを迫害します。それでフランコが反乱軍を率いて蜂起し、内戦が始まったわけですが、バルセロナは左派の拠点として機能した町で、内戦終了後は徹底的な弾圧があったようです。
そのフランコに対する恨みが反マドリッド意識として残り、それがFCバルサとレアルマドリッドのクラシコを加熱させている要因ともなっています。
今でこそ、スペイン最大の観光資源となったサグラダファミリアも、観光客が見向きもしない時期は、バルセロナ市民は、横を睨みながら通り過ぎていたようです。
カソリック教会も、フランコ陣営だったからだとか。
そういう歴史的な宿命というものが、どこの町でも残ってると思います。
簡単に解消するものでもないですが、それを祭として昇華させることで日常生活を支障ないものにするという知恵が昔からあります。
中村俊輔が加入したことで、バルセロナダービーは日本人にとっては従来とはまるで違う様相を持つことになるわけで、それはそれで非常に楽しみですね。