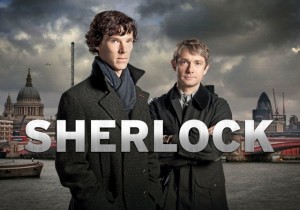[amazon_image id=”4103202211″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]「地球の歩き方」の歩き方[/amazon_image]
「地球の歩き方」の創刊30年の節目に、スタートした熱い4人の話をまとめたものを中心に出版されたものです。
地球の歩き方と言えば、世代によって様々なイメージを持ってると思います。
時代とともに旅の手段や方法、スタイルが変わってきましたが、日本の若者の傍らにはこの本が常にあったと思います。
「歩き方」メンバーは、1970年代前半からの活動のスタートですから、僕が初めて使った91年は、スタートから20年経った円熟期だった訳です。
そのときの「歩き方」の持つ独特の気配が何をルーツとしていたのかもよくわかるいい本でした。
91年に最初に旅は、大学の卒業式が終わったあとで、有り合わせのお金をかき集めて中国行きのフェリーに乗り、そのままユーラシア大陸を放浪することになったのですが、、、旅のあとで就職することになる設計事務所の所長から、フレーム式のバックパックを借りて行きました。
その所長も若い頃、ヨーロッパを放浪してて、その話をさんざん聞いていたこともおおいに影響を受けてました。所長が旅したのが、ちょうど「歩き方」創刊直前の時期だったと思います。
所長の熱い旅のエネルギーと同じ熱さを、創刊時の4人から感じましたし、旅というものの意味も熱かったんだと思います。
中国だけ旅行するつもりだった僕は、「歩き方中国編」と日本円のチェックだけ持っていました。その後、パキスタンやイラン、トルコ、ギリシャに行くのですが、当然情報は皆無。通貨の名称も、陸路で出入国する町も知らないという状況。
日本人と出会うと、夜に「歩き方」を借りて、行きそうな都市の情報をノートに書き写す日々。面倒になって、次第に、バスターミナルと安宿街がだいたいどのあたりにあるか、美味しい飯屋がどのあたりにあるか。その程度になっていきました。おかげで今でも、町の気配を読んで行動するのはかなり得意ですね。
イランは当時日本語のガイドブックが存在しなかったのですが、陸路で旅する人たちが、紙にイランでの旅情報をメモした「イランへの道」という数枚のコーピーがありました。いろいろな人が書き加えていたり、書き直されていたり。バージョンもたくさんありました。
究極のガイドブックです。
最初に「歩き方」を作った人たちは、そういうものを目指していたんでしょうね。
旅をする人が、同じ道を行く人に伝えるメッセージ。その感謝の気持ちを次の旅人に伝えることで、旅の時空間が醸し出されていくということ。
旅のフロンティアがなくなってしまった現在、情報誌としての「歩き方」の使命は終わってしまったと思いますが、逆にあふれる情報とどういう距離感を持って自由に旅をするのか?という状況でしょうね。