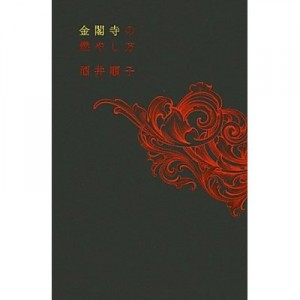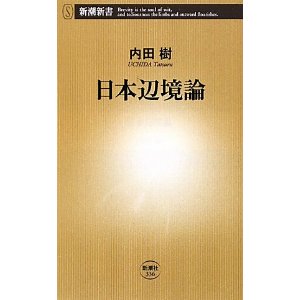[amazon_image id=”409386196X” link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]のぼうの城[/amazon_image]
息子に勧められて読んでみました。
寝る前に読み始めて、次の朝、早起きして読み続け、仕事前にギリギリ読了。
なぜか涙がぼろぼろ。
豊臣秀吉が天下統一直前の小田原攻めの時期。
小田原方の一支城をめぐる守備方と攻撃方のドラマ。
守る側は、(でく)のぼう率いる坂東武者たち。
攻める側は、石田三成率いる近江商人たち。
時代の流れを決定づける小田原攻めの裏ストーリーでありながら、時代の流れに反する渾身の戦い。
それが実は、次の次の時代の幕開けともなる皮肉な結末。
主人公が、劉備っぽかったのは若干残念。