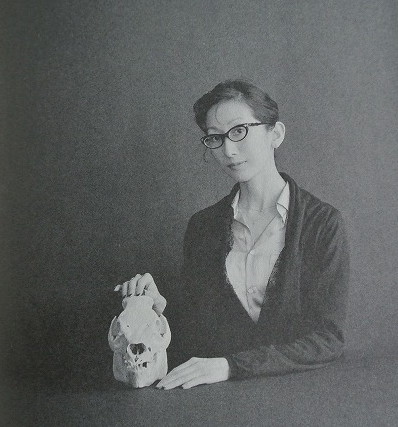読書メーターという読んだ本や読みたい本を登録し、他の人の書評などとリンクして楽しめるサイトがあります。去年の秋から始めてみて、219日で156冊。1日平均0.7冊のペースで本を読んでいるようです。年間250冊、月に20冊ペースというところです。
建築の本や歴史の本、サイエンスや料理の本などジャンルは幅広く、著者も多い人で2冊までですから、一つのテーマでも複数の視点の本を読んでるといえますね。
ここ数カ月で面白かった本を少しピックアップしてみます。
振り返ってみると、日本やアメリカ、欧州が今後どうなっていくのか?そのあたりが一番気になるところですから、そういう本をいくつか読んでいます。
現在の建築や生活文化のルーツは気になるところですので、何がどのあたり時期のものをルーツとしているのか?ということがいくつかはっきりしました。
歴史に関する本は、あまり対象範囲を広げないようにしようと思いつつ。。。
●経済に関する本
[amazon_image id=”4478017158″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門 もう代案はありません[/amazon_image]
円高、デフレなど日本の経済にのしかかる重いダメージの理由を、シンプルなマクロ経済から解き明かしてくれます。
[amazon_image id=”4047102334″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]デフレの正体 経済は「人口の波」で動く (角川oneテーマ21)[/amazon_image]
デフレが止まらない。理由は簡単で、生産年齢人口が減っているから。
じゃあどうすべきか・・ということが書かれています。
地方の経済を長く分析している著者なので、現状の把握が具体的です。
[amazon_image id=”412102124X” link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]日本経済の底力 – 臥龍が目覚めるとき (中公新書)[/amazon_image]
日本の経済の希望を感じさせてくれます。
●建築に関する本
[amazon_image id=”4306052389″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]建築家・吉田鉄郎の『日本の建築』―JAPANISCHE ARCHITEKTUR,1952 (SD選書)[/amazon_image]
吉田鉄郎氏が半世紀前にドイツ語で書いた日本建築史の本を和訳したものです。
異文化の人に説明するために書かれたものなので、解りやすく、奥が深いものとなっています。
住宅や庭について書かれたものも和訳されているのでぜひ読んでみたい。
[amazon_image id=”4562047488″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]サグラダ・ファミリア: ガウディとの対話[/amazon_image]
アントニオ・ガウディやサグラダファミリアに関する本はたくさん出ていますが、この本は写真も外尾さんの文章も素晴らしい。
●住まいに関する本
[amazon_image id=”4782411057″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]江戸時代 日本の家―人々はどのような家に住んでいたか[/amazon_image]
日本の伝統的と思ってる住宅の形式や要素の多くは、江戸時代の武家の住まいを由来とするものが多いようです。
[amazon_image id=”4022734159″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]世界一のトイレ ウォシュレット開発物語 (朝日新書)[/amazon_image]
TOTOのトイレ開発の中心人物が書き下ろしたウォシュレットの開発秘話。
日本が誇るウォシュレットはいかに偉大なのか?そう思わずにはいられません。
●その他の本
[amazon_image id=”4766001737″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]花森安治のデザイン[/amazon_image]
[amazon_image id=”4306072746″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]アメリカ大都市の死と生[/amazon_image]
[amazon_image id=”406258400X” link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]平清盛 福原の夢 (講談社選書メチエ)[/amazon_image]
[amazon_image id=”4880083240″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]悲劇のヴァイキング遠征―東方探検家イングヴァールの足跡 1036‐1041[/amazon_image]
[amazon_image id=”4062584387″ link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]アーリア人 (講談社選書メチエ)[/amazon_image]
[amazon_image id=”439113134X” link=”true” target=”_blank” size=”medium” ]腸をきれいにする特効法101―腸内細菌のバランスが全身の健康を左右する![/amazon_image]